紙の契約書に印紙を貼って、という常識が、いま大きく変わりつつあります。
2022年の宅建業法改正で不動産取引の電子契約が全面解禁され、2025年の現在は「売買契約もオンラインで完結」が当たり前になってきました。
コロナ禍を経て定着した非対面ニーズとDXの流れが、三島市で40年、地域に根ざすアイ企画でも、この変化は日々の業務に直結しており、確実に実務が更新されています。
例えば、
- 三島市で相続した空き家を都内在住の相続人が売却するケース
- 県外や海外からの移住者が何度も来店せずにIT重説→電子署名まで進めるケース
こうした場面で、移動・郵送・再来店の負担を削減しながら、スピーディに安全に取引を進められるのが電子契約の強みです。
この記事では、現場目線で電子契約の仕組みと法的効力、メリット(コスト・スピード・安全性)、そして見落としがちな注意点を整理しました。
 たかの
たかの
導入のステップや、実際の活用例まで、初めて方でも全体像がつかめるよう具体的に解説します。
高齢のお客様やITが不安な方には紙/対面との併用も可能としており、地域のお客様一人ひとりに合った“無理のない電子化”をご提案します。
もくじ
電子契約とは?法制度と仕組み
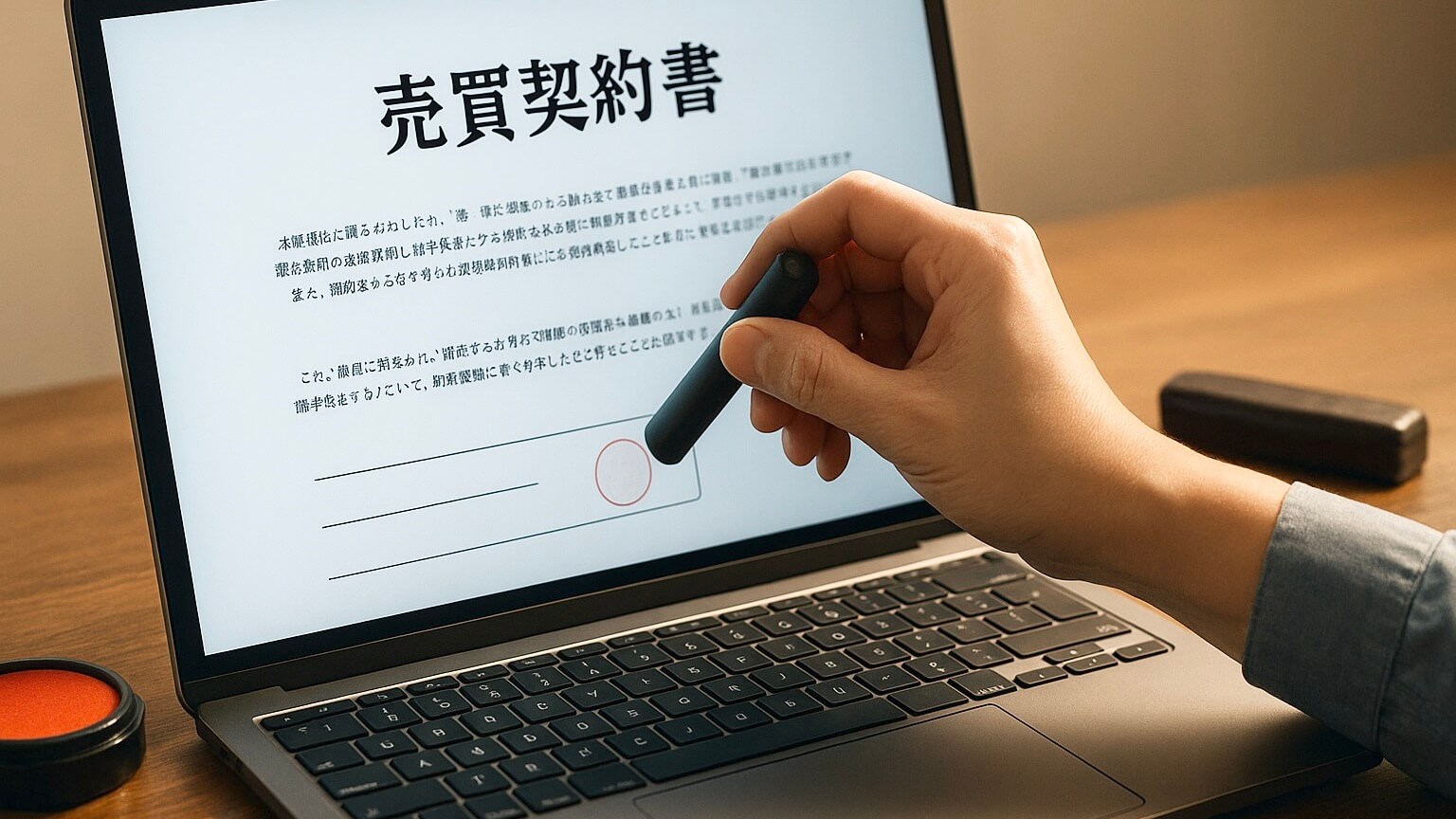
「電子契約」は、契約に関しての証拠となる契約書を紙ではなく、電子ファイルで作成する契約のことを指します。
電子契約では紙の契約書で使われる印鑑の代わりに、電子署名やタイムスタンプを使って、誰が作成したかを証明します。これらの技術により、文書が改ざんされていないことも確認できます。
電子契約の仕組みを活用することで書面契約と同様の法的有効性を担保できます。
電子署名法が与える法的効力
電子署名法は、本人による電子署名が付された電子文書について、「その電子文書は本人が作成したと推定」するルールを定めています。これが電子契約の根拠です。
電子署名及び認証業務に関する法律 第三条
一 電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
宅建業法改正で電子化できる書面
不動産売買で電子化できる主な契約書は、以下の通りです。
- 媒介契約書
- 重要事項説明書
- 売買契約書
- 賃貸借契約書
- レインズ登録証等
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
不動産を売買する際や賃貸借契約を結ぶ際には、物件についての重要事項を記載した書面を交付し、宅地建物取引士が説明することが法律で義務付けられています。
買主や売主へ説明する際に交付する重要事項説明書も電子化が可能です。
法改正前は宅地建物取引士による記名押印のうえ、書面交付していましたが、法改正にともない押印が不要となり、電子データによる契約締結が可能になりました。
電子契約の主なメリット
不動産売買の現場で“効く”メリットを、コスト・スピード・安全性・顧客体験の4軸で整理します。
弊社での実際の活用方法とともに詳しく解説します。
印紙税が不要で、数万円の削減に
紙の契約書には印紙税が課されますが、電子契約は課税対象外となります。
例えば、不動産売買契約書(紙)の場合、3,000万円の契約では印紙税1万円、8,000万円なら印紙税3万円が必要ですが、電子契約なら0円です。
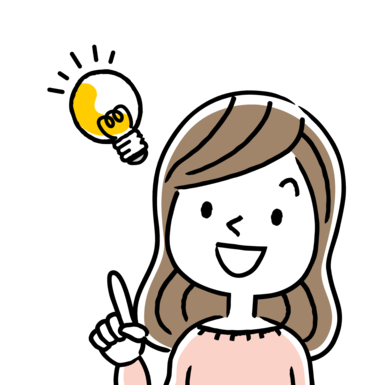 アイ子さん
アイ子さん
時間の圧縮で、郵送・再来店が不要
電子契約なら、契約書の印刷・製本・押印・郵送といった手間がなくなります。
遠隔地の売主・買主とも、同日中に締結できるのが大きな強みです。
 たかの
たかの
契約書を電子で安全に管理
電子契約書はクラウドやサーバーで体系的に保存でき、日付・金額・取引先名で検索が可能です。
電子帳簿保存法にも対応しやすく、税務・監査時の対応もスムーズです。
セキュリティ強化で、改ざん防止と記録の残存
電子契約は電子署名とタイムスタンプで改ざんを検知可能です。
さらに操作ログが残るため、誰がいつ署名したかを後から証明できます。
 たかの
たかの
顧客ニーズへの対応で柔軟な選択肢に
子育て層、県外在住者の中には「来店や押印は極力減らしたい」という方が増えています。
三島市内で電子契約を選択できる数少ない不動産会社として、こうした非対面志向のニーズにフィットしています。
 たかの
たかの
一方で、やっぱり紙で欲しいとお客様には従来通り紙の契約書を交付しています。
「電子契約と紙契約を選べる」という運用で、世代を問わず安心して取引できる体制を整えています。
電子契約の注意点

“早く・安く・安全に”を実現する電子契約ですが、法令上の前提や運用リスクを確認しないまま導入してはいけません。
現場でつまずきやすいポイントを、分かりやすく整理します。
相手方の同意取得が出発点
電子契約を行う際には、必ずお客様の同意が必要です。
実施前に、IT環境(メールの受信可否、スマホやパソコンでの閲覧可否、ダウンロードが可能かなど)を確認し、どの方法で電子書面を渡すかまで説明して承諾を得ます。
初めて電子契約を利用される方が多いため、弊社ではまず「承諾書そのものを電子契約で締結」して、実際の操作を体験いただくところから始めます。
また、承諾後であっても「やっぱり紙で欲しい」というご希望があれば、いつでも紙に切り替えることが可能です。
万一、電子書面がうまく開けないなどのトラブルが解決できない場合も、原則として電子交付は中止し、紙で対応しています。
 たかの
たかの
セキュリティ/バックアップ
電子契約では、セキュリティ対策とデータのバックアップが重要です。
契約書には電子署名とタイムスタンプが付与されるため、「誰が・いつ署名したのか」「その後改ざんされていないか」を確認でき、紙の契約以上に信頼性を高めることができます。
ただし、パソコンだけに保存していると故障や誤操作で消えてしまうリスクがあるため、クラウドや外付けHDDなど複数の場所に分散して保存(多重バックアップ)することが大切です。
また、不動産売買契約は長期保管が前提となるため、定期的にタイムスタンプを更新したり、長期署名(LTV)を利用して、将来にわたって真正性を確認できる状態を維持する必要があります。
さらに、アクセス権限を限られた担当者に絞り、契約システムには二段階認証や最新のセキュリティ更新を導入することで、情報漏えいや不正アクセスのリスクを抑えることができます。
高齢者・ITが苦手な方への配慮
電子契約は便利で効率的ですが、お客様の中には「スマートフォンやパソコンが苦手」「紙の書面で確認したい」という方も少なくありません。
弊社では、そうした方々にも安心して不動産取引を進めていただけるよう、以下のような配慮を行っています。
紙契約との併用運用
電子契約を推進しながらも、ご希望があれば紙の契約書を交付できる体制を整えています。
特にご高齢のお客様には、これまで通り対面での契約・説明を選んでいただけるようにしています。
店舗やご自宅でのサポート
IT環境をお持ちでない方には、店舗に来店いただき、スタッフと一緒に画面を操作して電子契約いただけます。
また、体調や移動の都合で来店が難しい方には、ご自宅に伺ってサポートすることも可能です。
柔軟な切り替え対応
電子契約の同意をいただいた後でも、「やっぱり紙が良い」と感じられた場合は、いつでも紙契約へ切り替えられます。
電子交付がうまくできない場合も無理に進めず、原則として紙に戻す安全策を用意しています。
売買契約書を電子化する流れ
売買契約を電子化する流れをステップごとに整理し、併せて弊社の取り組みも交えて分かりやすくご説明します。
事前に契約書や説明書を電子データでお渡しし、お客様のIT環境(メール・端末)を確認したうえで、「電子契約で進めてもよい」という承諾を記録します。
初めての方には「承諾書そのものを電子契約」で体験いただき、不安を解消してから本契約に進んでいただきます。
金額・特約などの内容をしっかり確認し、改ざんできない状態にして保存します。
社内で「ファイル名の付け方(例:2025_三島市旭ヶ丘_売買_4500万)」を統一し、後から探しやすくしています。
ITが苦手なお客様には、店舗で一緒に画面を操作したり、ご自宅でサポートする体制も用意しています。
長期保存が必要なため、定期的にバックアップを更新します。
電子帳簿保存法にも対応できるよう、保存ルールを明確にし、経理・税務とも連携しています。
まとめ
電子契約はすでに法的に整備され、今後の不動産取引の主流となることは間違いありません。
- コスト効率(印紙税不要・郵送費削減)
- スピード(遠隔即日締結)
- 安全性(改ざん防止・証跡管理)
この3つのメリットを享受しながら、顧客への丁寧な説明や法令遵守、業務体制の整備が導入成功の鍵です。
アイ企画では、電子契約の利便性を活かしつつ、高齢者やITに不慣れな方も安心して契約できる環境を大切にしています。
紙・電子のどちらも選べる柔軟な体制と、スタッフによる丁寧なサポートで、お客様にご満足いただける取引を目指しています。
「最短でスマホ完結」も「対面で一緒に操作」も、お客様に最適な方法をご提案します。





